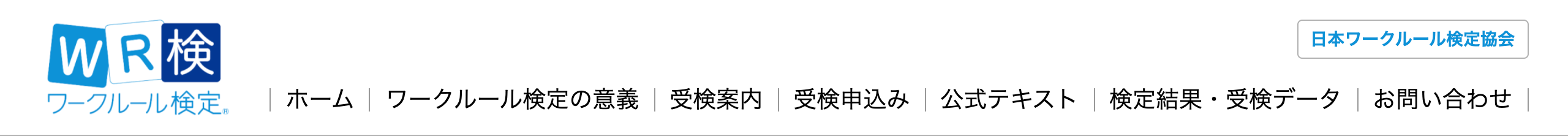-
K様 2025年春、初級と中級を受検

30年ほど中小企業で経理や総務全般の実務を担当してきました。
様々な事象に対応した際の知識を持つことはできましたが、判断に迷う度に労働基準監督署へ電話をして対応、その繰り返しでした。
「正しい」を知るため、「正しい」方向へ進めるべくワークルール検定を受検しました。学習し受検して、自信に繋がりました。知識が増えると、事象を繋げて考えることが増えました。
事前、事後の対応もどのように動けばよいのか、正しい知識は、正しい対応に繋がります。
昨今、制度の変更も多いですが、基礎を知ることで変更の理解にも繋がります。
私個人、今後の「ワーク」の光となりました。学び続けたいと存じます。 -
R様 2025年春、初級と中級を受検

現在、社労士を目指しています。
前職はスポーツのインストラクターをしていました。
大学時代の就職活動は知識や準備が不足しており、求人票の見方も分からないまま、周囲と比較して焦り、早期に入社を決めてしまいました。その結果、早期退職に至りました。
退職後は「働くこと」への不安や恐怖を抱えていましたが、地元の広報で社会保険労務士講座の募集を見かけ、母の勧めもあり学習を開始しました。勉強を進めるうちに、自分を守るための知識が身につくことを実感し、この知識を活かして他者も守れる社会保険労務士になりたいと強く思うようになりました。ワークルール検定は、社会保険労務士試験科目のうち「労働基準法」や「労務管理その他の労働に関する一般常識」と重なる部分が多く、社労士試験の良い練習になると考え、受験を決めました。
実際に受検してみると、社労士試験よりも問題文が分かりやすく構成されており、これまで曖昧だった知識が「こういうことだったのか」と理解できる場面が多くありました。その結果、社労士試験の学習が以前よりもスムーズに進むようになりました。
-
N様 2019年初級、2020年と2021年に中級受検

数年前に、労働環境を良くしたいと、仲間と労働組合を立ち上げました。
現在はUAゼンセンと全労連と二重加盟しています。
組合活動に役立てるため、その関連の知識を身につけたいと思い、ワークルール検定を受検しました。問題集を解いて2019年に初級は合格し、中級は、2020年秋と2021年春に受検したものの不合格となりましたが、中級の講習動画を何回か視聴し、2021年冬に再チャレンジし、3回目に合格しました。学習し、受検して、組合活動でなんとなく聞いてきた「不当労働行為」等の組合用語の他、労働者が法律でどう定義されているか等改めて知ることが多く、知識が深まりました。
労働問題にさらに関心が強くなってきたと感じます。
最近では、自分が活動している労働組合で、ワークルール検定で得た知識を仲間と共有しています。
今回内容が大幅に改定されることを知り、知識のアップデートするため2025年秋にまた中級を受検しようと思っています。